Topic
 発達性読み書き障害
発達性読み書き障害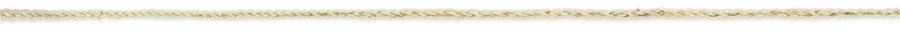
発達性読み書き障害は、知的能力や全体的な発達に遅れはないのに、文字の読み書きがうまくいかない状態のことです。普通に聞いたり話したりするのに、読んだり書いたりすると間違ったり時間がかかったりします。医学的には限局性学習症と呼ばれますが発達性読み書き障害、学習障害、発達性ディスレキシア等、色々な呼び方があります。数の概念の理解、計算、数学的な推論などが苦手な算数の限局性学習症もあります。
![]()
よく気付かれる症状として以下のようなものがあります。
*音読が苦手で疲れてしまう
*一文字一文字拾い読みする(逐語読み)
*単語や文節の途中で区切りを入れてしまう
*文末を間違って読む
*音が同じ助詞を間違う
*文字を書くのに時間がかかって疲れてしまう
*似た文字を間違える
*特殊音節が書けない
*読み方の変わる漢字が読めない
*漢字が覚えられない
*英語の読み書きの習得が難しい
小学校に入る前だと、文字に興味を示さない、しりとりができない等で気づかれることもあります。
頑張って学習してもうまく習得できない事で学習意欲がなくなったり、不登校の原因になったりします。読み書き障害の中学生の半分程度が不登校を経験するという調査もあり、早く気づいて、適切な支援を開始することが大切です。
![]()
令和4年の文部科学省の調査では「読む」または「書く」に著しい困難を示す小中学生は3.5%程度と推定されています。これに対し、欧米では10~15%とされています。日本語の平仮名は一つの文字に一つの読み方が原則ですが、英語のアルファベットは一つの文字に複数の読みが存在するため、読み書きの問題が生じやすいと考えられています。日本語でも漢字は複数の読みが存在しひらがなに比べるとつまずく子が多くなります。
これらの症状は、音韻処理機能や視覚情報処理機能、自動化機能の問題に起因すると考えられています。
この機能は、読み書きの習得や言語発達に重要な役割を果たします。特に、ひらがなやカタカナの習得に大切です。
視覚情報処理機能とは、文字を目で見てすばやく認識し、それを音読につなげる力のことです。音読するためには、まず文字を「目」で捉え、それを「脳」で処理し、「声」に出す必要があります。このとき、視覚的な情報(文字)を効率よく処理する機能が重要になります。特に、ひらがな・カタカナ・漢字を見分けたり、単語の形を素早く認識する力が関係しています。
音読の自動化機能とは、文字を見たときに、無意識にスムーズに音読できる力のことです。私たちは文字を覚え始めた頃は1文字1文字を読んでいたのが、練習を重ねるうちにすばやく正確に読めるようになります。
初めて本を読む子ども → 「あ…り…が…と…う」と1文字ずつ読んでしまう
音読の自動化が進んだ人 → 「ありがとう」とすぐに読める
このように、文字と音の対応が無意識レベルでできるようになることを「音読の自動化」といいます。これが発達すると、読むスピードが速くなり、内容理解もしやすくなります。
また、発達性読み書き障害の39%の子供がADHD(注意欠陥多動症)、64%がASD(自閉症スペクトラム症)を合併するといわれています。そのことからくる認知のアンバランスも読み書きに影響を及ぼします。
![]()
![]()
支援方法は読み書きの正確さや速さを改善する支援と苦手な事を補助代替する支援に分けられ、お子さんの年齢と状態によって、適切な目標を設定した上で必要な支援を計画します。的確な支援を行うために読み書きの苦手さの原因を神経心理学的な検査で確認し、その子に適した支援を計画することが大切です。例えば視覚認知からの記憶が苦手で聴覚認知からの記憶が得意なタイプのお子さんでは漢字の書き順を言語化して覚えたり、語呂合わせで覚えたりします。また知っている単語が多い方が文章の理解が容易になるので意識して語彙の習得に努めることも大切です。
読み書きの補助代替については、聞く話すに問題はなく、読む書くというoutputの問題なのですから、outputの部分を代替手段で乗り切ります。近年、ICT(information and communication technology)の発展により、使用できる手段が増えました。具体的には文章の読み上げ(人による読み上げ、ICTによる読み上げ)や漢字のルビ振り、音声付教科書の使用、ワープロの使用、音声入力等が考えられます。kindle等の電子本でも読み上げ機能が使用できますし、パソコンやiPadのアプリケーションで文章の読み上げや、音声からの文字起こしも容易にできるようになってきました。こういった支援を合理的配慮を理解した上で学校と協力して進めていくことが望ましいです。
![]()
Dougenzaka Fujita Clinic道玄坂ふじたクリニック
〒150-0043
渋谷区道玄坂1-10-19糸井ビル4階
TEL 03-5489-5100
FAX 03-6455-0864