Topic
 注意欠如多動症の正しい診断と不適切な診断治療の危険性
注意欠如多動症の正しい診断と不適切な診断治療の危険性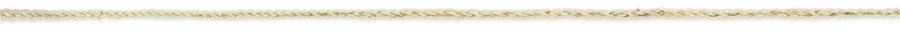
注意欠如・多動性障害(ADHD)の診断の基本についてはいろいろな資料がありますので、ここでは正しい診断のための留意点について述べてみたいと思います。それは、ADHDでないのにそう診断されて、治療薬の副作用に悩んでいる例が多く来院されるからです。また、ADHDは後述するように年齢とともに、中枢神経の発達に伴って徐々に軽減していくのにも関わらず、年長になっても同様の薬物療法が続けられている例も多々みます。しかし、必要のなくなった抗ADHD薬を続けることは、無駄なだけでなく、運転免許取得/維持や生命保険加入に支障を来します。これらを順に述べていきます。
1. ADHD含め発達障害は生来性です!
ADHDに限らず発達障害は生来性の認知機能障害です。稀には生来性に注意の欠如があったが、幼少期にはそれが目立たず、年長になって学校や社会で要求されるものが増えたために困難を意識しだしたという例もあり得るとは思います。特に、近年は「大人の発達障害」として、年長あるいは大人になってからADHD症状が目立つ例が多いといった報告もあります。しかし、発達歴を詳細に聴いても幼少期の異常が見当たらないという例はあくまで例外的であって、安易に幼児期からの症状の連続性の確認を省略して診断すると、後述するような紛らわしい病気/病態をADHDと誤診して、問題を複雑化するリスクをましてしまいます。実際にそのような例が来院することが多々あるので第3項で紹介します。
2. 自閉症スペクトラム障害(ASD)との併存について
ASDの子どもには、特に幼少期には注意の欠如や多動が目立つことが多く、この時期には半数ほどの子どもがADHDの基準を満たすようです。ASDでもADHDでもそれらの併存例でも、刺激過多にならないようにしたり、生活/学習環境を構造化したりすることが望ましいということは共通しています。しかし、ASDとADHDが併存した例への薬物療法となると、極めて慎重にする必要があります。一見して同じ集中困難にみえても、その様相はかなり違っています。ASDが併存していないADHDの子どもの集中困難は、「算数ドリルは一応やってくれるが、2〜3分で飽きてしまう」といった感じです。これに対してASDの子どもの集中困難はその様相がかなり違っていて、「もともと頭の中が、昆虫でいっぱいなので、そもそも今算数といわれても嫌だもん!」といった感じです。さて、抗ADHD薬のうちで、メチルフェニデート徐放薬(コンサータ)やリスデキサンフェタミン(ビバンセ)は、今集中していることの持続時間を延長するように働くようです。このため、上述のある意味純型ADHDのようなタイプには非常にプラスに働きますが、もともと昆虫で頭がいっぱいというタイプの場合は、昆虫タイムが延びるだけで、やってもらいたい算数へと行動を切り替えることは反って困難になります。この状態で無理に行動を切り替えようとすると時として以前にはなかった暴力が出現することもありますので、一層慎重になる必要があります。実際にこういったことが起きて、学校から手に負えなくなったと言われて困り果てた親子が相談に来ることがしばしばあります。他の抗ADHD薬であるアトモキセチン(ストラテラ)もASD併存例に対してはよりリスクがあるようです。この薬は抗うつ薬に類した効能を持つノルアドレナリン再取り込み阻害薬であるため、その有害事象も抗うつ薬と一部共通しています。添付文書にも、易刺激性、攻撃性、自殺念慮/自殺関連行動などが記載されていますが、これらについては学校などとも情報を共有した上で、最大限の注意を払う必要があります。もう一つの抗ADHD薬であるグアンファシン((インチュニブ)についても添付文書に易刺激性、自殺念慮/自殺関連行動のリスクが記載されていますので同様の注意が必要です。
3. 紛らわしい他の病気/病態
基本的にADHDの症状は、集中困難や多動ですから、中枢神経の病気でこれらに影響するものや、脳の代謝を悪化させるような身体状況では紛らわしい状態を呈することが珍しくありません。そして、抗ADHD薬のうちで流通規制がある薬剤やリスデキサンフェタミンのような覚醒剤原料が誤診に基づいて処方されることはあってはならないことですし、他の抗ADHD薬を含め有害事象が比較的多い薬剤ですから、ユーザーの利益のために慎重な診断が求められます。
(1) ナルコレプシーや特発性過眠症
これらの病気では過剰な眠気がありますから、当然集中力の問題が生じてきます。ADHD-RSのような専門家による症状のチェックでも、「もぐらーず」のような評価アプリでも不注意と関連した所見がでてきます。しかし、これらの疾患に用いられるモダフィニルのドパミン系に対する作用は抗ADHD薬による作用よりもマイルドなものです。このため、これらの疾患をADHDと誤診して精神刺激薬を処方した場合、ドパミン刺激が過剰になって、その結果、頭痛、不眠、食欲不振、興奮などが現れてしまった例もあります。
(2) 甲状腺疾患、副腎皮質疾患
甲状腺機能については、低下、亢進両方とも結果として不注意が現れることがあります。甲状腺機能亢進症に関しては、脳が過剰に活性化されて、怒りっぽくなったり、注意があちこちに逸れやすくなったりすることがあります。それ以前に甲状腺機能亢進症にあっては、精神刺激薬は心血管系への影響を増強させてしまうリスクから投与禁忌になっています。甲状腺機能が低下している場合には、脳も含めた全身の活動性が低下して、不注意が現れる場合があります。また副腎皮質機能低下症においてはやはり脳や心臓を含めた全身の働きが鈍くなって不注意が現れた例もあります。これらに対して抗ADHD薬を投与された場合は、そもそも原因が異なりますから、結果が全く予想できないので、最大限の注意を払う必要があります。
(3) 鉄欠乏性貧血(IDA)
貧血がある場合は、脳血流量が変わらなければ、脳に流入するヘモグロビン量が減るわけですから、それに並行して脳に流入する酸素量が減少することになります。貧血の要因が鉄欠乏である場合はそれだけではなく、脳を含めた全身の細胞でのエネルギー産生が減少することになります。エネルギー産生に関わる酵素の中で鉄を活性化に必要とするものがあるからです。こういった理由もあり、一定以上の鉄欠乏性貧血では認知機能が低下するという報告もあります。この場合においても抗ADHD薬の作用は予想困難であるため、IDAがなくともADHD症状があるのかどうか慎重に判断する必要があります。
(4) 空腹、低血糖、やせ
就職や進学などと関連した初めての一人暮らしで、朝食抜きの生活と関連して午前に強い不注意が出現して来院された例が複数あります。脱水による血圧低下による不快感や低血糖による脳機能低下によって不注意が発現したもののようです。何例かで、朝食をしっかりとり、脱水にも気を遣うことによって午前の不注意が消失しました。またやせすぎも問題となります。低血糖によって上述の例と似たことになりますし、強いやせは低T3症候群といって、甲状腺ホルモン低下を来して、不注意を惹起することがあります。
(5) 睡眠時無呼吸症候群(SAS)や肥満低換気症候群(OHS)
肥満や向精神薬の影響によって、SASが発症/増悪することはよくあり、精神科患者の治療においては大きな問題です。また、肥満低換気症候群といって、一定以上の肥満で
は呼吸運動が浅くなってしまい、その結果二酸化炭素貯留が起きて更なる呼吸抑制が起きる状態となります。これらは夜間の低酸素によって睡眠中の脳の回復が阻害されたり、昼間に持ち越した低酸素によって直接的に認知機能が障害されたりして、不注意をもたらします。このような場合に必要なのは、SASやOHSの治療を地道に続けることが肝要です。低酸素だからといって、早まって酸素スプレーや酸素カプセルで酸素補給をするなどということは極めて危険です。普段低い酸素飽和度が急に上昇すると、呼吸が止まってしまう怖れがあります。
(6) 薬剤性の過鎮静
抗精神病薬や抗不安薬・睡眠薬は不注意を惹起します。また、抗うつ薬も運転に関連した研究によると注意力を減弱させるようです。このような状態をADHDと誤診するとまるでアクセルとブレーキを両方踏んでいるような治療となり、効果がなく、有害事象のみ現れているようなことがしばしばみられます。また、抗ADHD薬でもたらされた不眠に対して睡眠薬が併用されたり、昼間の不安感に対して抗不安薬が併用されたりした例をみることがありますが、これでは折角、抗ADHD薬で改善した集中力を抗不安薬やハングオーバーした睡眠薬で相殺することになってしまいますので、極力抗ADHD薬の減量やその上で学習環境を構造化することを検討することが推奨されます。
4. 年齢とともに軽減するということ−運転免許などと関連して−
ADHDの症状の多くは、年齢とともに軽減していくということは重要な事実です。小学校入学時にはADHDの有病率は約7%といったことになっていますが、15歳頃には2%くらいと見積もられています。成人後はさらに低い有病率となります。これは有病率がただ低下するのみではなく、個々人においてADHD症状が軽減することによって、診断閾値以上の例が減少することを意味しています。したがって、思春期以降は、薬の力なしで日常性や学習行動を遂行できる可能性が高くなってきます。一方で、抗ADHD薬は添付文書において全て運転禁止を意味する記述があります。このためバイクや自動車の運転免許を取得したり維持したりすることが困難になります。また、向精神薬を服用していると生命保険などの契約において、通常の掛け金で加入したり契約更新したりすることが困難であるようです。思春期以降の治療継続に際しては、これら服薬治療に伴う社会的なデメリットがあることをご本人、ご家族と共有した上で慎重に考える必要があります。
![]()
Dougenzaka Fujita Clinic道玄坂ふじたクリニック
〒150-0043
渋谷区道玄坂1-10-19糸井ビル4階
TEL 03-5489-5100
FAX 03-6455-0864