Topic
 統合失調症
統合失調症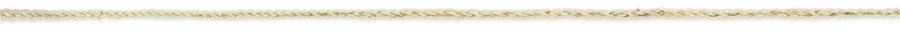
統合失調症は精神科で診療する主な疾患の一つであり、特に入院設備のある精神科では入院患者の多くを占める疾患でもあります。典型的な統合失調症は、発症間もない急性期に陽性症状と呼ばれる幻覚、妄想や興奮がみられ、それに続く慢性期に意欲減退や感じ方が鈍くなる陰性症状がみられます。後で詳しく述べますが、全ての患者がこのような典型的な経過を辿るわけではありません。また、世界中どこで調査しても人口の0.5〜1%にみられる疾患です。このことから、その原因はまだはっきりしていませんが、個人的な素質と環境両面で多数の要因が重なって発症するものと考えられます。治療法は、薬物療法、ストレス軽減、リハビリなどが確立しており、これらを適切に実施していることで、回復、病悩期間の短縮を促すことができます。
1. 統合失調症の症状
統合失調症の症状は大まかに初期から現れる陽性症状と慢性期に現れる陰性症状に大別されます。統合失調症は多くの場合、本格的な発病前に前駆期と呼ばれるなんとなく不安定で心身の調子が悪い状態が数日から数週間続きます。この時期には不眠やなんとなく落ち着かない感じや体調不良が出現しますが、他の精神疾患や体の病気と区別がつかないことが多いです。その後、急性期ないし活動期と呼ばれる幻覚★1、妄想★2、精神病性の思考障害★3、興奮や昏迷★4といったいわゆる陽性症状が目立つ期間が1か月から数か月続きます。この時点で治療(薬物療法が主体)が成功すればより短期間で終息します。これに引き続いて慢性期、残遺期ないし回復期と呼ばれる期間が2か月から数年続き、この期間には意欲の減退、易疲労性などといったいわゆる陰性症状が目立ちます。後で治療のところでリハビリについて述べますが、一見して陰性症状に見えるものが、病気でお休みしていた時に心身が訛ったための言わば心身の廃用症候群である部分も多いようで、この部分はリハビリによって短期間で回復する場合も少なくありません。以上に述べたような陽性症状が1か月以上、陰性症状も含めて半年以上症状が続いた場合、統合失調症と診断されます。また以上の症状の全てがみられるわけではなく、以前妄想型と言われたタイプでは幻覚、妄想が目立ち、同じく解体型と言われたタイプでは精神病性の思考障害が目立ち、緊張型と言われたタイプでは、興奮や昏迷が目立ちます。
★1幻覚: 実際には存在しない音声が聴こえたり、実際には存在にないものが見えたりするといった知覚の異常.
★2妄想: 実際とは違うことを信じてしまって、思い違いの修正が難しい.
★3精神病性の思考障害: 会話の中で思考の連続性が薄れて、会話がだんだんと関係がない内容になってしまったり、極端な場合には前後の文章の関係が不明で意味をなさない発言になってしまったりする.一般に、辻褄が合わないなどと表現されることがある.
★4昏迷: 周囲の刺激に反応が乏しくじっと動かない状態.
2. 統合失調症と近縁の疾患
前項に述べたような症状が一定期間続くと統合失調症と診断されますが、より短い持続期間で治った場合には、短期精神病性障害(1ヶ月以内)、統合失調症様障害(1ヶ月超え6ヶ月以内)と診断されます。また、症状が妄想だけの場合には妄想性障害、上記症状と気分障害の症状が同様に目立つ場合は統合失調感情障害と診断されます。これらに加えて、体の病気や薬剤によって、統合失調症類似の症状を来す場合がありますので、慎重な鑑別診断が必要です。特に麻薬性の薬剤によって、数時間から数日にわたって上記のような症状が惹起される場合があり、この場合は治療法や予後が全く異なってきますので鑑別が大切です。近年、抗NMDA受容体抗体関連脳炎と呼ばれる自己免疫疾患が統合失調症様の症状を呈することが分かってきましたが、この疾患は普通の統合失調症と誤認して治療されると治療薬が奏功しないばかりか、さまざまな不随意運動、呼吸障害や昏睡状態が現れてくる場合が多いため正しい診断が肝要です。
3. 統合失調症の原因について
原因について述べる前に、まず、統合失調症というのは単一の病気ではないようだということをご理解いただきたいと思います。多くの身体疾患は、生物学的なマーカーが存在していて、たとえば、甲状腺機能亢進症のほとんどを占めるバセドウ病を例にとれば、甲状腺ホルモンが高値であり、病気の原因となっている抗TSH受容体抗体が陽性であれば、ほぼ間違いなく診断できます。それと比較して統合失調症の場合は生物学的なマーカーが存在しないため、上述のような症状とその持続期間によって、症候群として、つまりいくつかの症状の組み合わせによって診断されています。このため、単一の病気である保証はなく、むしろ、いくつもの原因によって、結果として上記のような症状を呈した例が総称として統合失調症と呼ばれているのだと考えてください。そのため、薬剤による改善も個人差があり、予後にも個人差があります。また、世界中どこでも0.5〜1%の有病率であることから、多数の遺伝要因、環境要因が重なって発病しやすさが決まっていると思われます。単一の遺伝子が原因である遺伝病は、その遺伝子異常の作用が顕性か潜性かによってメンデルの法則に従って遺伝するはずですが、統合失調症ではそのようなことはありません。また高血圧症のように、10個か20個程度の遺伝素因が大きな影響を持つものでは、家族集積性がもっとハッキリしていますが、統合失調症はそうでもありません。また、遺伝素因のみが大きな疾患では、その遺伝素因が多い人が住んでいる地域で有病率が高くなりますが、統合失調症はそういったこともありません。また、特定の環境で発症率が著明に上昇することも証明されていません。これらのことを考え併せますと、上述のように多数の遺伝要因、環境要因が重なって発症するものと思われます。
4. At Risk Mental State(ARMS)について
多くは10歳代にみられるARMSと呼ばれる病態があります。心身が過敏になり、視線が気になる、人から悪く思われていないかどうか気になる、自分の想いや臭いが人に影響を与えてしまっている気がする、幽霊のようなものが見えた気がするといった、統合失調症を疑わせるような訴えが、断片的にあるいは軽度にみられるような状態です。このような状態の場合は、できるだけ日常の生活、勉学を続けながら、ストレス軽減のための短時間の相談を続けることが役立ちます。そうすると過半数の例では、1年くらいの間に症状は消退します。しかし、ごく一部が統合失調症やその周辺の疾患に移行しますから、定期的な病状観察が必要です。ここで注意すべきことは、統合失調症のような薬物療法は最小限度に留めることです。アメリカなどでの過去の報告をみると、この状態から本格的な統合失調症に移行するのを阻止するために、早めに統合失調症に対するような薬物療法を始めても、統合失調症の発症予防ができないばかりではなく、薬の副作用によって体重増加などが生じ、身体の健康を損なうことがあるという結果のようです。一方で、必要な時には適切な抗精神病薬の標準量を上手く使うことも大切なことです。症状が遷延して社会生活に多大な影響がある場合、特に統合失調症に移行していると考えられる例には、薬物療法を躊躇すべきではありません。薬物療法が不十分であったために、長く引き籠ったり、周囲との衝突を繰り返したりした例も珍しくはありません。
5. 統合失調症の治療と予後
統合失調症の治療の要点は、(1)抗精神病薬によって陽性症状を抑える、(2)ストレスを軽減する、(3)リハビリによって陰性症状を軽減させるという3点にまとめることができます。以下にそれぞれを概説し、最後に病気の予後を述べます。
(1) 抗精神病薬
抗精神病薬は脳内のドパミンを始めとしたモノアミンと呼ばれる一群の神経伝達物質の働きを抑える作用があります。このことによって、脳内の過剰な情報伝達を収めて、幻覚や妄想を軽減させると考えられています。半世紀以上前に開発された定型抗精神病薬という種類の、クロルプロマジンやハロペリドールなどの薬剤は主としてドパミンによる神経伝達を担うD2ドパミン受容体の働きを部分的に遮断することによって症状を抑えます。2000年前後から開発されたリスペリドンやオランザピンを代表とする非定型抗精神病薬という種類の薬剤はドパミンのみではなく、セロトニンやノルアドレナリンやヒスタミンなどの神経伝達物質の働きを広い範囲で抑えて、症状を軽減させます。新しい非定型抗精神病薬は定型抗精神病薬と比較すると、手が震えるなどの錐体外路症状という副作用は少ないのですが、代わりに体重増加などの全身への副作用がより強い傾向があります。抗精神病薬は陽性症状を抑えるために有用ですが、これらの副作用対策を同時にやっていく必要があります。特に非定型抗精神病薬の場合は、食欲が増進しますので、毎食食べる量は決めておいて、それをオーバーしない注意や、体重を継続的にチェックすることなどが大切です。
(2) ストレス軽減
過大なストレスは病状再燃のもとになると言われています。仕事量を適正にするとか、まだ十分病状が安定していない時期には通常よりも就労時間を短縮するなどの注意が必要です。ストレスは精神的なものだけでなく、身体的なストレス、すなわち過労や身体病なども精神面に悪影響を及ぼすため、これらも良い状態を保ちたいものです。また、感情表出(Expressed Emotion: EE)という概念が以前から提唱されていましたが、30年ほど前から簡便に測定できるようになり、研究が進み、患者を取り巻くストレスの要因として重要視されています。EEとは家族や患者の身の回りの人々から患者に向けての批判的な感情や巻き込まれすぎの程度を表すもので、これらの程度が高いと再発率が高まると言われています。患者の周囲は、患者に対して批判的になりすぎないように、また、感情的になりすぎないようにすることが良いようです。
(3) リハビリ
上述のように、抗精神病薬の服用やストレスの軽減によって、統合失調症や近縁の疾患の陽性症状の制御や再発防止には一定の効果をあげることができます。しかし、この病気にみられる陰性症状の軽減や、心身の廃用症候群の改善のためにはリハビリが必要です。統合失調症に限らず、あらゆる心身の病気においては、休養によって体力低下や対人的な過敏性が生じてきます。体力低下は身体疾患で2週間ほどの入院生活によって起こってきて、職場や学校への復帰の妨げになります。また、他に病気がない場合の不登校であっても、外出がない生活を続けると、人目が気になり、どう見られているかを過剰に気にするようになります。このような状態を改善するためには、1対1の相談やカウンセリングよりも、適度な運動や、他者とともに過ごす時間を回復していくリハビリが効果的です。精神科治療施設ではデイケアや作業療法などのプログラムがありますが、短時間のアルバイトも役立ちますし、毎日、一定時間の図書館での勉強なども役立ちます。
(4) 統合失調症の予後
予後については、長らく1/3はほぼ回復、1/3は寛解しない状態が続く、残りの1/3はその中間などと言われていましたが、最近のデンマークの研究(Starzer
2023)では、7割が5年以内に陽性症状が改善、3割が陽性症状持続あるいは再発、陰性症状については半数が持続と報告されています。
![]()
Dougenzaka Fujita Clinic道玄坂ふじたクリニック
〒150-0043
渋谷区道玄坂1-10-19糸井ビル4階
TEL 03-5489-5100
FAX 03-6455-0864