Topic
 市販薬の意外な副作用にご注意!
市販薬の意外な副作用にご注意!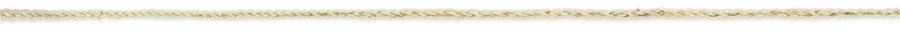
私の小児科の大先輩の好きだった言葉に、「クスリはリスク」というのがあります。回文になっていますが、要するにクスリである限りはリスクがあるということです。麻黄という生薬が入った漢方薬の副作用でちょっとびっくりした経験と、時々出会う市販の消炎鎮痛薬による高血圧についてご紹介します。それぞれ症例をあげてありますが、個人情報を保護するため、個人を特定できるような情報は削除した上で、複数例をブレンドしてあることをご了承ください。
1.
麻黄含有の漢方によって著しく怒りっぽくなってしまった一例
症例1. 患者の付き添いで来院された40歳代の女性が、あまりに怒りっぽいので、精査をお勧めしました。どういうことかというと、付き添いで来院されたのですが、私の目の前で連れてきた患者を批判し続け、どうみても尋常ではない興奮状態でした。聞いてみますと、怒りっぽくなったのは最近2週間ほどだと言います。収縮期血圧は140mmHg台と高めで、脈拍も100/分 前後と頻拍気味でした。急激に始まった怒りっぽさですので、精神科の病気である気分障害の躁状態のほかにも、薬剤性によって惹起された興奮状態や、甲状腺機能亢進症による興奮状態を想定して、服用している薬剤をまずお聞きしました。すると、新型コロナ感染症を予防するつもりで、2〜3週間前から、漢方薬である麻黄湯を毎日欠かさず1日3回服用しているということが発覚しました。後述するようにこれが興奮状態の原因と考えて即刻中止してもらいました。すると翌日には穏やかな状態を取り戻したということでした。ちなみに後日結果が出た甲状腺機能は正常で、甲状腺疾患は否定されました。
麻黄には覚醒作用のあるエフェドリンが含まれており、風邪などの初期に短期日用いることで薬効を発揮します。また、その注射製剤は手術時の血圧低下に対してよく用いられてきました。しかし、エフェドリンは覚醒剤の原料ともなる化合物で、10%以上を含むものは覚醒剤取締法の規制対象でもあります。もし麻黄を本例のように比較的長期間服用し続けると、エフェドリンによって中枢神経が刺激され続けて、病的な興奮状態を来すことがあります。このような例があることは、古典的な漢方の本にも記述がありますが、残念なことに漢方薬の添付文書にはあまり強い警告は記述されてしません。麻黄湯や葛根湯など麻黄が配合された漢方薬を服用するときには、エフェドリンによる興奮状態が惹起される可能性を意識しておくことが望ましいです。
2.
時々出会う消炎鎮痛薬による高血圧
症例2. 会社の残業が多く、過労気味でさまざまな身体症状を来して相談に来られた50歳代女性。初診時の血圧を測定すると収縮期血圧160mmHg台でした。お話しを聞いた後でもう一度測定しても同様で、何度量っても160〜170でした。これまでに高血圧を指摘されたことはないとのことで、薬剤性を疑いました。それで分かったことは、長時間労働で惹起された筋収縮性頭痛に対して、ロキソプロフェンやイブプロフェンを含む鎮痛薬をこの数週間常用しているということでした。後述のように、個人差はありますが、消炎鎮痛薬の連用は血圧上昇を来すことがありますので、より影響が少ないアセトアミノフェンに替えてもらって、上記の薬剤は中止してもらいました。その結果、3日後に再来したときには高血圧は消失していました。
ロキソプロフェンやイブプロフェンは、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAID)と呼ばれる痛みを軽減するために用いられる代表的な薬剤です。この種の薬剤は作用がはっきりしているため解熱や鎮痛の目的でよく用いられます。そして、薬としては歴史も長く、医療用や一般薬としてよく用いられています。体内での働きは、シクロオキシゲナーゼ(COX)というアラキドン酸からプロスタグランジンE2(PGE2)やプロスタグランジンI2(PGI2)を合成する酵素を阻害することによって炎症を抑え、ひいては痛みや発熱を抑えます。ところが、PGE2やPGI2には、腎臓の動脈を拡張して腎血流を増加させる作用があります。そのため、NSAIDによってその生成が抑えられると、腎血流が減少して、腎臓からの水分の排除が不十分となって、血管内に水分が貯留して血圧が上がることがあるのです。もちろん、腎血流や血圧はさまざまな要因で調節されており、NSAIDを連用しても、血圧上昇が置きにくい人も居ます。しかし、誰しも、前もってNSAIDによって血圧が上がりやすいか上がりにくいかは分かりませんから、もしも、NSAIDを連用するような場合には時々血圧を測定した方が良いでしょう。NSAIDには、腎血流を減少させるリスクの他にも、胃を痛めやすいとか、インフルエンザや新型コロナ感染症などのウイルス感染症の悪化リスクを高めるなど幾つかの副作用がありますから、特に連用する場合には医師や薬剤師との相談が必要です。特に子どもに投与する解熱・鎮痛薬は、特別な理由がなければアセトアミノフェン一択にすべきです。
![]()
Dougenzaka Fujita Clinic道玄坂ふじたクリニック
〒150-0043
渋谷区道玄坂1-10-19糸井ビル4階
TEL 03-5489-5100
FAX 03-6455-0864