Topic
 減薬を検討しましょう!
減薬を検討しましょう!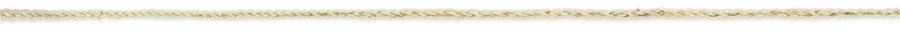
向精神薬はその作用によって助かっている人が多い一方で、その副作用によって困ったことになっている人も多いのです。(1)ベンゾジアゼピン作動薬(抗不安薬、睡眠薬)、(2)抗うつ薬、(3)抗精神病薬、(4)精神刺激薬のそれぞれについて、その過量投与や長期投与のリスクと減薬の仕方について述べてみます。
(1)
ベンゾジアゼピン作動薬
ベンゾジアゼピン作動薬はその化学構造によって、ベンゾジアゼピン系薬剤と非ベンゾジアゼピン系ベンゾジアゼピン作動薬に分けられます。いずれもベンゾジアゼピン受容体に作用して、抗不安作用や催眠作用や筋弛緩作用をもたらします。非ベンゾジアゼピン系ベンゾジアゼピン作動薬は名前が「z」で始まるものが多いことからZ薬とも呼ばれ(zopiclone: マイスリーなど)、その一部はベンゾジアゼピン系薬剤よりもふらつきなどの副作用が軽いともいわれています。これらの薬剤は上述のような臨床的に有用な作用を担ってくれる一方で、ふらつきによる転倒や物忘れや認知機能の低下をもたらすこと、また、嚥下障害をもたらす可能性も指摘されています。また、円滑な日常生活や身の回りの危険を避けるための不安も減弱してしまうので、そのことと関連したリスクも懸念されます。抗不安薬による衝動行為の増加などを指摘した報告もあります。衝動行為をした時の心配、不安も薄れてしまうようです。お薬には、その人に有害な不安と必要な不安の見分けはつきませんからこれは仕方がないことです。これらのリスクを考えると、必要がなくなったら、これらの薬剤は減量、中止していきたいものです。しかし、残念ながら、お薬の減量方法を間違ったために、本来は減量、中止できる薬剤の減量、中止を諦めてしまう方が多いのが現状です。中枢神経は適応能力が著しく、これら不安を弱めるお薬を投与されると、「可笑しい、急に不安レベルが減弱した!」と察知して、逆に不安を増強するように神経系を再調整します。だから、お薬を急にやめると過敏になった神経系はリバウンド不安を感じてしまうことになります。このリバウンド不安やリバウンド不眠を予防しつつ、減薬するためには、お薬の減量幅をワンステップ10〜20%、人によっては5%ほどにとどめ、ワンステップの減薬になれるために2週間、人によっては1か月かける必要があります。また、ロフラゼプ酸(メイラックス)のように、血中半減期が5日間にも及ぶ薬剤は脳内にはさらに長く停留することが想定されるため(ひとたび脳内に入った薬は、肝臓で代謝されることがなくなるため)、減量や中止をしてから1か月もしてからリバウンド不安やリバウンド不眠が生じます。このような場合、更に緩徐な減薬で乗り切ることができるはずですが、残念ながら多くのユーザーは、これを減薬によるリバウンドではなくて、「ずっと薬を続けなければならない病気を患っている証拠」ととらえてしまいます。薬を中止しても1週間以上何も起こらないので、中止によるものとは思わず、病状の悪化と勘違いしてしまうのです。いずれにしてもベンゾジアゼピンの減薬、断薬は一人一人に合ったペースで緩徐にやっていけば達成できることを知っていただきたいと思います。
(2)
抗うつ薬
抗うつ薬もうつ病が寛解してから半年を経れば減量中止が可能なことが多いです。しかし、このグループの薬もゆっくりと減量していかないといわゆる離脱症状といって、めまいや吐き気や感覚過敏を惹き起こすことが多いのです。抗うつ薬の急激な減量や中止で起こる感覚過敏は、音に敏感になったり、頭の中でシャンシャンと鳴っているように感じたり、明るいところで酷くまぶしく感じたりするといったとても不愉快な症状として起こることが多いのです。特に、パロキセチン(パキシル)やベンラファキシン(イフェクサー)では極めて丁寧に減量しないとこのような症状が出やすいようです。しかし、これらの症状も慎重な減薬によって乗り切って、減薬、断薬が可能なことが多いです。抗うつ薬の長すぎる継続は、薬の非特異的な鎮静作用による怠さや、生活の変化が億劫になって何をするのも面倒になり、感情が鈍くなるといった薬剤性のアパシーを惹き起こすことがありますので、不用意に長期間な継続は避けたいものです。
(3)
抗精神病薬
21世紀になって、統合失調症の治療の主役が非定型抗精神病薬であるリスペリドンやオランザピンになってからは、病状が寛解しても減量しない医師が増えています。前世紀に用いられていたハロペリドールなどの定型抗精神病薬と比較して目立った副作用が少なくなったために減量の必要性を医師も患者も感じ難くなったためです。しかし、非定型抗精神病薬の過剰な長期投与は、感受性の鈍麻や認知機能への負の影響や不随意運動のリスクがありますので、病状が安定した後は、積極的な減薬が必要です。しかし、抗精神病薬は中枢神経への情報の入力を部分的に遮断するのですから、その急激すぎる減量は精神病の症状を一過性に再燃させることがあります。これを過感受性精神病といっています。つまり、抗精神病薬による情報入力の遮断によって、脳は、「可笑しいな、情報が足りないな!」と感じて、感受性を増強しているのです。この状態での急激すぎる減薬は脳にとっては情報過多となって、一時的に幻聴や猜疑心といった精神病症状を再燃させてしまう場合があります。これは一過性に終わり、病気の再発にはつながらないことが多いのですが、このことを知らないと医者も患者も、「たいへん!病気が再発した!」と思い込んで抗精神病薬を増量してしまいます。ここで最も大切なことは、減薬はゆっくり、リスペリドンのような高力価抗精神病薬では、クロルプロマジン換算でワンステップ50mg、リスペリドンにして0.5mg、また、クロルプロマジンのような低力価抗精神病薬ではワンステップでクロルプロマジン換算25mgの減薬にとどめることです。そして、減薬のワンステップにはその人に合わせて1週間から1か月かける必要があります。
(4)
精神刺激薬
このグループの薬はADHDに対してよく処方される、メチルフェニデート徐放薬(コンサータ)やリスデキサンフェタミン(ビバンセ)です。これらの薬剤も長期投与になりやすいのです。集中力を増強して、勉強時間を延ばしたり、スポーツの成績を向上させたりしますので、その効果自体が、薬への依存心を惹き起こすからです。しかし、集中力を前借するような薬ですから、夕刻になって薬効が切れてくるとリバウンドで意欲が低下したり、急激な中止で虚脱状態を惹き起こしたりしがちです。また、夕刻になっても作用が持続する人の場合は夜間の不眠などを惹き起こします。それに対して睡眠薬を処方するようなことが行われることがありますが、朝に残った睡眠薬の作用によって、折角の精神刺激薬の作用がキャンセルされているといった、一体何のための処方なのかわからなくなっている事態も散見されます。もっと良くないのは、元気の前借によって生じたうつ状態に対して抗うつ薬が投与されているのを見たことがありますが、抗うつ薬による食欲増進・肥満、精神刺激薬と抗うつ薬による過敏性増強で、引き籠りが悪化していました。このように良いばかりの薬剤ではないのですから、思春期以降、発達によってADHD症状が軽減したら、減量中止を考えたいものです。また、国内では全ての抗ADHD薬は運転してはならないことになっていますから、免許が取れる16歳とか18歳までにはこのグループの薬はゼロを目指したいものです。このグループの薬剤はベンゾジアゼピンや抗うつ薬と比較したら、減薬、中止がより容易なことも知っておいてください。
![]()
Dougenzaka Fujita Clinic道玄坂ふじたクリニック
〒150-0043
渋谷区道玄坂1-10-19糸井ビル4階
TEL 03-5489-5100
FAX 03-6455-0864