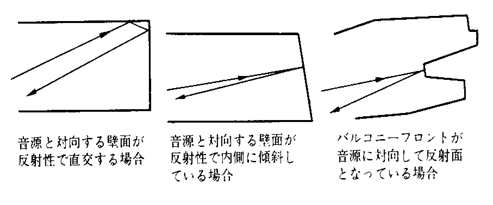
エコー続き
エコーの発生をなくすためには17m以下の距離差にすればいいといいましたが、それをしてしまうと大変小さなコンサートホールしか作れなくなってしまいます。そのために壁や天井を吸音処理したり、拡散処理をすることで回避します。これにつきましては別に詳しく書きます。
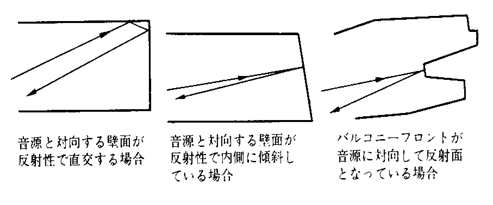
上がエコーの出やすい断面図パターンです。音が入射する壁面に吸音処理をすると、反射音が壁に吸収されるためエコーが出なくなりますが、吸音を強くすると残響時間も短くなるの(
残響について の項目を参考してください)で、吸音と拡散処理を併用してエコーを押さえるようにします。
ところで、エコーの中にも特殊なエコーなるものがあります。日光東照宮に行ったことがある人は知っているかと思いますが、鳴き竜というのがあります。これはフラッターエコーといって特殊なエコーです。これは平行な壁と壁、天井と床というような関係で発生します。手をたたくとその音が平行する反射面の間を往復して、ブルブルブルもしくはビビビという妙な音になり聞こえます。日光の鳴き竜はこれをわざと起こすようにしたものですが、通常の室内でこれが起こる場合は音響的には最悪となります。(フラッターエコーのエコータイムパターンは
前のページ にあります。)
このフラッターエコーはエコーの中の特別な形と書きましたが、結構フラッターエコーの出る場所があります。周りの音によってわからない場合が多いのです。例えばあなたの教室(平行な面が存在する部屋)がコンクリート構造などであればフラッターエコーを体験できるかもしれません。人がいない放課後などに教室の真ん中で手をたたいてみてください。妙な音に聞こえませんか?ただし、教室の壁などに吸音材(穴あきボード、クロスなど)が張ってあればフラッターエコーは出ません。コンクリなどの反射率の高いものが平行になっていると出る現象ですから・・・。