| 1.ランチェスター戦略の歴史 |
イギリスの航空工学のエンジニアであったF・W・ランチェスターは空気力学の研究で著名な人だが,第一次大戦で自らが手掛けた飛行機が実戦に使われたのを見て,戦争や戦闘に強い関心をもち,空中戦をシミュレーションすることで,ある法則を発見した。これがランチェスター法則である。これらの研究の成果は1916年に著した「戦争と飛行機-第四の武器の曙」にまとめられている。
その後,このランチェスター法則は,アメリカでコロンビア大学の数学教授バーナード・O・クープマンらのORチームによって,さらに研究された。軍事戦略のシュミレーションモデルのランチェスター戦略モデル式が作られ,第二次大戦後期において,軍事戦略として,特に中部太平洋り対日戦線に使われ多大な成果を収めたのである。以後,アメリカではOR(オペレーションズ・リサーチ)に発展していった。
わが国では,1962年,私の師であった田岡信夫が販売戦略としてのランチェスター戦略を構築,従来の精神主義,根性論を排除した科学的かつ実戦的な販売戦略として高く評価された。特に「強者の戦略」「弱者の戦略」を概念ではなく,具体的な形にしたところはマーケティング戦略の革新といってよい。
ランチェスター戦略は英国で生まれ,米国で育ち,日本で花開いた。「ランチェスター戦略は汗の臭いのする戦略である」といわれたことがあるが,日本で育った戦略だからなのである。
ランチェスター戦略は,一般の方の目に触れるようになってから,既に50年近いの歴史をもつ。一部には「ランチェスター戦略は古い」という声もないわけではないが,逆に今こそランチェスター戦略の原点に戻らなければという企業も多いのも事実である。 |
| 2.ランチェスター法則 |
①ランチェスター第一法則
M0-M=E(N0-N)
M0…M軍の初期兵力数
M …M軍の残存数
E …武器の性能,腕前
N0…N軍の初期兵力数
N …N軍の残存数
戦闘力=E×兵力数
第一法則は,個対個の戦いで,一般に「一騎うちの法則」と呼ばれている。古代の弓矢,刀,槍など一人が一人を狙い撃つ,一騎うち型の兵器を使った戦いは,
いかに兵力が多くとも,戦いは個対個,つまり一騎うちの積み上げである。
このような戦いは,初期兵力数の差によって勝敗が決まってしまう。孫子の兵法には「互角の兵力なら勇戦せよ,劣勢なら退却せよ」というのがあるし,またプロイセンの戦略家として有名なクラウゼウィッツも「兵力の優越は,戦勝を決する最も重要な要素であり,数の多い方が勝つ,ということが戦略の基本である」としている。
ランチェスターは,このような一騎うち型の戦いを上記の式で表した。
仮にE=1(武器の性能や腕前が同じ)とすると,敵を全滅させるには,
M0-M=N0,すなわち,M0-N0=Mとなる。

たとえば,E=1で,M軍5人とN軍3人が戦えば,3人はEが同じなため,互いに相撃ちとなり,5-3=2で,N軍が全滅したときにM軍は二人残るのである。
つまり,兵力の多い方が,多い分だけ残って勝つということになる。この第一法則は,「弱者の戦略」の基本となる。
こちらの「何でもランチェスターの法則」で、ランチェスターの第一法則、第二法則のシュミレーションが出来ます。
|
②ランチェスター第二法則
M02-M2=E(N02-N2)
戦闘力=E×兵力数2
仮にE=1とすると,敵を全滅させるには
M02-M2=N0,すなわち,M02-N02=M2となる。
第二法則とは集団対集団の戦いで,一般的には「確率戦闘の法則」とか「集中効果の法則」と呼ばれている。また,二乗がつくため,「二乗法則」とも呼ばれるが,通常ランチェスター法則といえば,この第二法則を指す。集団と集団の戦いでは,大砲や機関銃が使われるため,
戦いは広域的かつ確率的なものとなる。ランチェスターは,このような確率的な戦いを上記の式で表した。
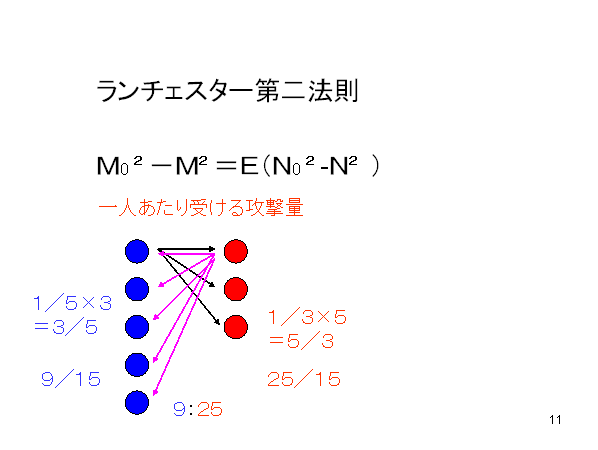
たとえば,M軍5人とN軍3人が戦えば 52-32=16=42で,N軍が全滅したときにM軍は四人も残っていることになる。さきの第一法則では二人しか残らなかったのだから,兵力数の多い方は第二法則で戦ったほうが,はるかに有利になるのである。
これは,一人当たり受けている攻撃量が,相手兵力の二乗になるためだ。 二倍の兵力は四倍,三倍の兵力比は九倍という差が開いてしまう。
日本海軍はこれを「N2の法則」と呼んでいた。この法則は,今日のORの出発点になったもので,アメリカではランチェスター賞が設けられ,毎年ORの優れた研究者には多額の賞金が授与されている。この第二法則は,「強者の戦略」の基本となる。
こちらの「何でもランチェスターの法則」で、ランチェスターの第一法則、第二法則のシュミレーションが出来ます。 |
| 3.マーケットシェアの目標値と射程距離理論 |
1)シェアの目標値
ランチェスターの発見した第一法則,第二法則は,その後アメリカで第二次大戦中,軍に徴用されたコロンビア大学の数学の教授バーナード・O・クープマンをはじめとするアメリカ海軍作戦研究班ORチームの手によって研究が進められた。戦闘は長引くと,兵力や武器の補給,兵力の訓練や武器の生産などの要因が発生することを考慮して,ランチェスター戦略モデル式が作成されたのである。
このランチェスター戦略モデル式から,斧田太公望氏と田岡信夫が,ゲームの理論や微分積分を駆使して導き出したものが,三つのシェア目標値である。
それぞれ以下の意味をもつ。
○上限目標値73.9%
これは「独占的寡占型」と呼ばれ,首位が絶対安全,優位独占の状態である。新ランチェスター戦略では,「これ以上のシェアはとるべきでない」と解釈している。
○安定目標値41.7%
競争において優位に立つことを考えると,通常半分以上,つまり50%以上のシェアを取ることが目標になる。しかし,ランチェスター戦略モデル式からは首位独走の条件として41.7%の数値が導き出された。
実質3社以上の戦いの場合,41.7%以上のシェアを取ると,業界の主流になるばかりでなく,独走態勢に入ることが出来る。一般的には40%として使われている。
○下限目標値26.1%
1位といっても,その地位が不安定で,いつ逆転されるかわからない1位もある。この安定,不安定を分ける数値が26.1%である。26.1%を越して,はじめてドングリの背比べから抜け出すことができる。トップが下限目標値に至っていなければ,まだシェア争いは決着していないとみてよい。
以上の3つの目標値は①シェアの位置づけ,②今後のシェアの目標値として使うべきものである。たとえば,1位でシェアが上がって26%を越えたら,いよいよドングリの背比べから抜け出したと判断することになるし,40%を越えたら,独走態勢に入ったと見て頂ければよい。また,シェアが現在23%なら,26%を目標にすればよい。
 ※最近、上記以外の目標シェア、例えば19.3%、10.9%、6.8%、2.8%をランチェスター戦略の目標シェアとしている人がいる。これは上記の目標値をかけあわせたものであり(26.1×73.9など)、昔のランチェスター戦略にはなかったものである。(だいたい、かけあわせること自体が論理的ではない)世の中には色々な考え方があるから、ランチェスター戦略のシェア目標値に関しても色々な数値があるのは当然ではあるが、ちょっと考えてみるとおかしいことがよくわかるはずだ。 ※最近、上記以外の目標シェア、例えば19.3%、10.9%、6.8%、2.8%をランチェスター戦略の目標シェアとしている人がいる。これは上記の目標値をかけあわせたものであり(26.1×73.9など)、昔のランチェスター戦略にはなかったものである。(だいたい、かけあわせること自体が論理的ではない)世の中には色々な考え方があるから、ランチェスター戦略のシェア目標値に関しても色々な数値があるのは当然ではあるが、ちょっと考えてみるとおかしいことがよくわかるはずだ。
まず、シェアの分母の定義(競合関係にある商品や企業)がわかっていないことに加えて、そもそも、ランチェスター戦略では小さくてもいいからNO.1を作るというのが鉄則なのであるから、2.8%の目標値などはまるで意味がないし、そんな企業はいつまでたってもNO.1になれるはずがないのである。あくまでも上記3つのシェアを目標にすべきである。
2)射程距離理論
射程距離はランチェスター戦略モデル式から,斧田太公望氏氏と田岡が導き出したもので,特定2社間における一騎打ち型の戦いや局地戦では,戦力が√8(約3)以上,広域的,総合的な戦いでは√3倍以上離れてしまうと相手にされない(勝ち目がない)ということが示された。これを射程距離と呼んでいる。射程距離とは,弾やミサイルが届く距離をいうが,企業間競争では,逆転できる,できないという距離を表している。
(先にふれたアメリカのORチームは,3倍の兵力を投入すれば,戦いに勝てるばかりか,損害量も軽微になると提唱した。(これは上陸作戦でフルに活用された))
つまり,実質2社の戦いといえるような場合や,個々の顧客での戦いでは3倍,地域や商圏の戦いでは√3倍のシェア差があると逆転できないということになる。逆に言えば,これ以下の差なら十分逆転が可能なのである。もちろん,この射程距離は1位と2位だけではなく,1位と3位,2位と3位など,それぞれの間で適用できる。
シェアは100しかないため,競合企業の数によってシェアの数値は大きな影響を受ける。たとえば,板ガラス業界は国内メーカーはわずかに3社しかない。輸入品を合わせても,最下位のセントラル硝子でも18.3%(96年)のシェアがあるのに対して,日本酒業界は減ったといえども,まだ2千社以上のメーカーがある業界で,トップの月桂冠といえどもシェアは8%台しかない。現時点で,月桂冠が40%シェアや26%シェアも目指すのは大変難しいのである。
戦いは戦争も企業間競争でも,相対的なものだけに,シェアは市場において重要であることは違いがないが,相手との差の方がもっと重要だ。
こちらの「何でもマーケットシェア」で、射程距離などのシュミレーションが出来ます。 |
| 4.弱者と強者 |
1.戦略はそれぞれの企業で異なる
生産性アップ,合理化は企業共通のテーマであり,地域や社会に対する貢献なども同様で、業界で一位の企業だろうが、二位の企業だろうが、とくにやり方が変わるわけではない。しかし、マーケティング戦略は、企業の立場により内容が異なる。業界一位の企業と二位の企業で、マーケティング戦略は決して同じではない。逆に同じことをやっていては、シェアも順位も変わらないのである。つまりてマーケティング戦略はそれぞれ企業の立場で異なるべきものなのである。
2.弱者,強者とは
1)弱者とは
戦争や戦さでは兵力数の多い側が強者とはっきりしているが,企業間競争の場合の強者,弱者をどう判断したらよいか?人によっては,大企業は強者,中小企業は弱者,また大型店は強者,専門店や一般店は弱者というおおざっぱな判断をすることも多かったが,1位は強者。2位以下はすべて弱者である。
2)強者,弱者の判断とは
○場面で判断する
この強者,弱者は企業全体の売上規模で決まるものではない。あくまでも,特定な市場や地域でのマーケットシェアで決まるものなのである。つまり,場面で判断をすべきもので,たとえば味の素は総合食品メーカーという視点で見れば強者だが,マヨネーズでは弱者になるし,資生堂も化粧品は強者だが,シャンプー・リンスは弱者なのである。ビールでも,沖縄ではオリオンビールが強者なのである。他店舗展開している小売業でも,この店は1番店だから強者,この店は2番店だから弱者と判断しなければならない。
複数の事業部や部門,複数の店舗,広域なテリトリーをもつ企業は,この部門は強者,あの部門は弱者とか,この地域は強者,あの地域は弱者と,整理しておかなければならない。強者と弱者が混在している場合は,強者の戦略,弱者の戦略の使い分けが望まれる。
○新規参入は弱者
いうまでもないが,新しい市場に参入する場合は弱者である。たとえ,主力部門が強者でも,弱者の戦略をとらなければならない。
3)ランチェスター戦略は弱者の戦略
ランチェスター戦略はアメリカ軍の「物量作戦」イメージや各業界のトップメーカーが最初に活用・導入したことから,昔はランチェスター戦略は強者の戦略と思った人が多かった。しかし,ランチェスター戦略は攻めの戦略であり,攻めは弱者の戦略であるからだ。
強者の戦略は弱者の戦略の裏返しの戦略として作られたのである。これは弱者の戦略の方がより具体的であることで理解して頂けると思う。 |
| 5.弱者の戦略 |
1.基本戦略…差別化
差別化とは戦いにおいて武器の性能や腕前を上げることである。まともに戦ったら
まず勝ち目のない弱者は,武田信玄の騎馬隊や織田信長の種子島のように,
差別化した武器を使って勝ってきた。差別化はランチェスター法則でいうところのE(武器効率)を上げることなのである。
2.弱者の五大戦略
○局地戦で戦う
局地戦とは「一定地区の戦争」,つまり限られた範囲の戦いをいう。弱者は広い地域で戦っては,少ない兵力を分散させてしまい,ますます勝つ見込みがなくなってしまう。逆に狭い地域の戦いであれば,強者は強者たる力を発揮できないため,弱者にも十分勝つ可能性がある。今日の企業間競争でも同様なことがいえる。もともと総合力で劣る弱者が欲張って手を広げ,力を分散させてしまったら,ますます勝つ可能性がなくなる。 そこで,まともに戦ったら勝ち目のない弱者は勝てる場面を探すか,勝てる場面を作るしかないのである。
○一騎打ちで戦う
一騎打ちの戦いとは,「敵味方双方とも一騎ずつ出て勝負を争うこと」で「一対一」の戦いをいう。ランチェスターの第一法則でもあきらかなように,一騎打ちの戦いでは強者も弱者もそれほどの差はない。ということは弱者としても,勝つチャンスは十分あるのである。販売競争においても,弱者は一騎打ちの戦いをすることが望まれる。
1)他社と一騎打ちになっている市場や地域を重点化する
2)新規顧客開拓においては,他社一社独占顧客(オンリー顧客)を狙う
○接近戦で戦う
接近戦とは,文字通り「接近した戦い」という意味である。接近すればするほど,相手の強者は強者たる力を発揮しにくいし,こちらとしては強者の弱点を見つけ易くなり,攻撃もしやすくなる。北欧のバイキングの戦いや舞の海の相撲の取り方はまさにこの接近戦である。 戦争は敵と味方の直接対決だが,企業間競争は顧客の取り合いなわけだから,「顧客との距離を縮めた戦い」が接近戦になる。
具体的には以下の4つのテーマがある。
1)直接販売方式をとる
メーカーの場合,弱者は代理店や特約店を使った間接販売より,直接末端顧客に販売する直接販売方式が接近戦となる。
2)川下作戦を展開する
間接販売のメーカーが直販に移行するのは生易しいことではない。そこで,流通チャネルはそのままにしておいて,訪問活動だけは川下=末端顧客を回るのが川下作戦である。
3)地元から固める
地元とは本社・本店・支社・支店・営業所・出張所・工場・物流基地や企業発祥の地などの地域のことである。弱者は地元でも弱いことが多く,逆に地元から離れたところに力を入れようとするが,まず地の利を生かし,地元を固めることが先決だ。
4)スキンシップで戦う
強者は「○○(企業名)だから」という企業力で勝負している。それは強者がイメージや実績から,顧客に対して安心感を与えているからにほかならない。
イメージや実績で劣る弱者は,顧客との人間関係を作り,「△△さん」だからといってくれるファンを一人でも多く作ることが重要だ。
○一点集中
一点集中とは重点に置くべきものを決め,そこに力を集中することである。
戦いでは量が劣っていると,勝つことは難しい。弱者は全面戦争では勝てないから,ある場面に力を集中して勝つことを考えなければならないのである。 企業間競争においても,総合力で劣る弱者は集中攻撃をすることが望まれる。少ないヒト・モノ・カネを総花的に投入しては,ますます勝ち目はなくなるし,いつまでたっても現状を打開することはできないのである。地域や市場を細分化して,重点におくべきものを決めて,そこに力を集中することが一点集中である。
○陽動作戦
陽動作戦とは,一言で言えば「かくらん戦法」のことである。こちらの意図を隠し,敵の判断を間違いさせるよう,わざとある行動に出て,敵の注意をその方向に向けさせる作戦をいう。敵を心理的に動揺させたり,敵兵力を分散させることが狙いである。 |
| 6.強者の戦略 |
1.基本戦略…ミート
弱者の基本戦略は差別化である。差別化とは戦いにおいて武器の性能や腕前を上げることだが,弱者が差別化をしてきたら,強者は弱者と同様に武器の性能や腕前を上げればよい。そうすれば弱者の差別化の効果はなくなるのである。
たとえば,兵力の少ない弱者が鉄砲を持って来たら,強者も鉄砲を持てばよい。これをミート(追随)という。つまり,ミートとは弱者が差別化で上げたEを1に戻すことなのである。販売戦略においても同様に,強者は弱者の差別化に対してミートすることが必要だ。
2.強者の五大戦略
○広域戦
広域戦とは「広い範囲の戦い」をいう。弱者の場合は,広域戦では少ない戦力を分散させてしまうことになり,勝つ見込みがなくなる。そこで,谷地のような狭い地域で戦い=局地戦をしかけてくるのである。逆に強者としては,強者たる力を発揮できる広域な戦いをしたほうがよい。イメージとしては,>局地戦が桶狭間の戦い,広域戦が関ヶ原の戦いといってよい。 企業間競争でも同様に,弱者は局地戦を展開してくる。強者は弱者に弱者の戦略をとらせないようにすることが基本だから,なるべく広範囲の戦いをして,弱者に局地戦の場面を広げさせたり,局地戦を展開させないようにすることが必要だ。
○確率戦
確率戦とは確率的兵器,たとえば機関銃による戦いをいう。一人が一人を狙い打ちする戦いではなく,確率的に敵を撃つ戦いではランチェスター第二法則のとおり,兵力数の多い方が圧倒的に有利になる。強者は一対一の戦いを避け,弱者を数で押さえ込むことを考えなければならない。戦さでも三人以上でかかれば,どんな剣の達人でも勝てなかったといわれているし,太平洋戦争でもアメリカは必ず編隊を組んで戦ったのである。戦争や戦闘の場合は,敵対味方の戦いだが,企業間競争では数多くの企業が互いに戦っている。これ自体確率戦といってよく,その結果,企業間競争においては,強者はきわめて有利な立場にいるのである。
強者としては競合企業数の多い市場を重点においたり,併売率の高い顧客を狙うことが望まれるが,一歩進んで,自社内でも競争させることにより,死角を少なくし,弱者に食い込む余地を与えないことも考えなければならない。 たとえば,メーカーであれば製品アイテムを増やして製品同士を競争させたり,代理店・特約店同士を
競争させたり,営業拠点同士を競争させたりする。小売・サービス業では,自店間競合を意図的に起こし他社を進出させないようにすることが,確率戦である。
○遠隔戦
遠隔戦とは「遠く離れて戦う」ことであり,弱者の「接近戦」に対応するものである。
弱者が接近戦を展開するのは,接近すればするほど強者は力を発揮しにくいし,強者の弱点を見つけることができるからだ。逆に強者としては,接近せず,離れて戦うことが必要である。離れていれば戦局を冷静に観察できるし,強者たる力も発揮できる。但し,販売戦略は戦争と違い,顧客の取り合いだから,敵との距離というより,顧客との距離を置いた戦いが遠隔戦ということになる。
具体的には
・卸をフルに活用する
・広告宣伝を強化することが遠隔戦である
○総合戦
総合戦略とはすべての武器を総動員して戦うことをいう。総合力で劣る弱者は,ある局面に狙いを絞って全力を集中してくるが,強者はこれに対し,すべての武器を使い,かつ圧倒的な量で立ち向かうことが必要だ。
戦争において,強者が陸・海・空軍を大動員して,敵を壊滅させることなど,まさに総合戦といってよい。戦いでは戦力比で戦闘期間が決まる。戦力の差が大きければ戦闘期間は短くなる。圧倒的な量を投入すれば決着も速くつくのである。
また,総合戦になれば,部分的に弱点があっても,他のものでカバーすることが出来るし,攻撃力はたし算ではなく,かけ算で拡大するものなのである。つまり,総合戦は強者の強みをフルに発揮する戦いといってよい。
具体的には
・量で圧倒する
・品揃えを武器にする
・広域テリトリーを武器にするなどが総合戦である。
○誘導作戦
誘導作戦とは,敵をこちらの都合の良い方へ導く作戦をいう。弱者は手の内を読まれないために,陽動作戦を展開してくるが,強者はそれに惑わされないように,先手を打って弱者を思うように導くことを考えなければならない。古代の戦争での,谷底や行き止まりに追い込んで,上から石を落としたり熱湯を浴びせるなどは誘導作戦であり,近代戦では弱い部隊と思わせて,敵が攻撃してくるところを一気に叩くことなどがこの作戦にあたる。強者が敵の出方を掴んだり,敵を思うように誘導出来れば,もう勝敗は決まったようなものである。
企業間競争の場合も,敵を誘導するためには,まず敵の性格を把握しておかなければならないが,わが国の場合は強者がなにかをやると,マネしてくる企業が多いだけに,「マネ」をさせることが一番簡単な誘導作戦になる。 |
| 7.3つのポイント |
1.NO.1主義
NO.1主義は,NO.1になるという目標であるとともに,そのために,細分化したなかでのNO.1を作るという手段を表している。
もちろん,ここで言うNO.1とは,たんなる1位のことではなく,2位を射程距離以上離している1位のことである。
NO.1…1位 ≧ 2位 × √3
2.弱者・弱点優先攻撃の原則
1)弱者優先攻撃の原則
わが国の企業はどうしても情緒的発想が強く,上位それも1位企業に対する意識が強い。 これは1位に対するコンプレックスの表れであろう。特に2位の企業やかつて1位であった企業にこの傾向が強い。
しかし,2位以下の企業がまともに1位と戦っても,まず勝ち目はない。勝ち目があるのなら,とうの昔に勝っているはずなのである。戦いは勝たなければならない。
2位以下の企業は強い相手との戦いを避け,自社よりも弱い相手を叩いてシェアアップし,最後に1位と一騎打ちに持ち込むというステップを踏まなければならない。常に攻撃をかけるのが弱い敵であることから,「弱いものいじめの原則」と呼んだ。
競争目標とは当面逆転すべきであるから,相手は同等もしくはひとつ上位のライバル,攻撃目標とは顧客を奪取する敵のことで,相手は下位,それも足下の敵,つまりひとつ下の敵になる。
◎攻撃目標は足下の敵(ひとつ下の敵)
◎競争目標…頭上の敵(ひとつ上の敵)
2)弱点優先攻撃の原則
さらに,この「弱いものいじめの原則」に加えて,「他社の弱点をつけ」という意味もある。どんな強い企業でも,人間がやることゆえ,完全無欠ということはありえない。必ず手薄なところや弱い点を持っているものなのである。
たとえ,相手が上位の企業といえども,この死角や弱点を攻撃すれば,必ず道は開けるといってよい。
以上,「足下の敵を叩け」,「他社の弱点をつけ」という二つの戦略を,ここでは
「弱者・弱点優先攻撃の原則」と呼んでいる。
3.一点集中主義
この一点集中主義とは,市場を細分化し,そのなかから重点に置くべきものを決めて,40%のシェアを取るまで攻撃を続けるという意味である。
勝つための鉄則は集中化である。たとえ,強者といえども,人・モノ・金が有り余っているわけではない。力をいれるべきものを決めて,そこに力を集中することが必要だ。
特に弱者は1位に比べ,ヒト・モノ・カネが少ないのだから,総花的に力を分散していては,とうてい勝ち目はない。そこで,地域・商品・顧客層などを細分化し,その中で特に力をいれるべきものを絞り込むべきである。
 以上がランチェスター戦略の基本である。成功した企業について、ランチェスター戦略的視点で解説するのは簡単だが、問題はこのランチェスター戦略をビジネスにどう応用していくかがポイントである。 以上がランチェスター戦略の基本である。成功した企業について、ランチェスター戦略的視点で解説するのは簡単だが、問題はこのランチェスター戦略をビジネスにどう応用していくかがポイントである。
ランチェスター戦略に関するブログはこちら
矢野新一のランチェスター戦略のCDはこちらで販売しています。 |